
近年の農業における課題に、経済的な苦境がある。化学肥料や農薬、資材などの価格高騰によりコストがかさみ、「このままでは経営が続けられない」と危機感を抱く農業者も多いという。
その背景には、農業者が長らく感じてきた「工業的農業」への疑念も重なっている。現代の農業に化学肥料は欠かせない存在だが、生産量を上げるはずの化学肥料によって土壌が痩せてしまい、収穫を維持するためには化学肥料に依存するしかない……。「自分たちは何か根本的に間違っているのではないか」という切実な思いが、農業者の間で広がっているという。
この課題に、農業経済学の観点からアプローチしているのが、北海道大学大学院准教授の小林国之氏だ。
「農業経済学」は食糧生産や流通、農業者の所得の向上など、農業を経済的な側面で探求する学問で、小林氏が課題解決の方法として着目しているのが「リジェネラティブ農業」である。
これは再生型農業とも訳され「土壌を甦らせること」を目指す農法だ。海外では20年ほど前から実践が進められており、アメリカのノースダコタ州にある2000ヘクタールもの農地で農法を実践する農業経営者、ゲイブ・ブラウン氏が第一人者とされる。
そもそも、リジェネラティブ農業では、土壌をどのように捉えているのだろうか?着眼点は「土の中における植物と微生物の共生関係」にある。
植物は光合成で得たエネルギーや栄養素を微生物に与え、微生物はその見返りとして、土壌内のリンや窒素を植物が活用できる形に変えて植物に渡している。この循環を活性化させれば、過度に化学肥料や農薬に依存せず、作物が育ちやすい土壌が生み出せるという。
具体的な手法としては、農地をあえて耕さないことで土壌の乾燥や低温化を防ぎ、微生物が生きやすい環境を作る「不耕起栽培」や、農地に家畜を放牧して、微生物の餌となる糞尿を土に撒く、などの方法が用いられている。
もう一点、この農法の特徴として「正解も共通のプロセスも存在しないこと」が挙げられる。我々の体が一人ひとり異なり、健康になるためのプロセスが異なるように、農業でも土壌の性質や気候などの地域性によって、異なるアプローチが求められる。
加えて、リジェネラティブ農業を行う目的により、最適な手法やプロセスも変わってくる。土壌を健康に保って長期的に農業の生産性を上げたい人、農薬による農業者自身の健康リスクを回避したい人など、その目的によって化学肥料・農薬の使用の有無や、使用量が判断される。この点は、化学的に合成された肥料や農薬を使用しない「有機農業」や「自然農法」とは大きく異なる。
短期的な収穫量を増やすならば、化学肥料を使う農法は効率が良い。しかし、長期的な視点で考えた場合は、化学肥料を使い続けると作物の生産量は落ちてしまい、生産量を維持するためのコストが増してしまう。
小林氏がこの農法を研究しているのは「健康な土壌が作れたら、農業者は化学肥料や農薬を大量に買う必要がなくなり、農業経営が安定する」と考えているからである。農業経営の持続性という観点から、合理的な農法だと判断しているのだ。


小林氏はリジェネラティブ農業の普及過程も研究対象にしている。海外では草の根的に広まっている農法だが、どのような過程を経て普及しているのだろうか?
小林氏によると、まずは「土に対する認識の変化」が必要だという。土壌を「植物や微生物が生命活動を行う場」として捉えなおすことで、微生物と植物の共生メカニズムに目が向くようになり、農業者は土作りのプロセスを見直すことができる。
この認識の変化を促すのが、農業者同士の相互学習だ。実際にリジェネラティブ農業が行われる様子を見てもらい、実践してもらう。その中で得た「これならできるかもしれない」という実感が農法を変える原動力になり、さらに、学びや失敗を他の実践者と共有することで、より効果的な農法が模索できるという。
こうした実践の中で、「農業者の誇りが取り戻されることがある」と小林氏は話す。近代農業はマニュアル化を進めることで、どのような環境でも一定の収穫量が見込める農法を実現した。その恩恵はとても大きかったが、手法が画一化されることで農業者の自発性が損なわれている側面もあった。
「土壌を甦らせること」を目指して土を観察し、実践を重ねていく過程は、「農業」という営みに対する自発性を取り戻す行為である。人間もまた自然の一部だと思い出すことで、生命現象との関わりにやりがいを見出し、仕事に対する誇りを取り戻す人もいるだろう。高齢化による就農者の減少が心配されている昨今、新規就農者の獲得に関わるやりがいの問題は、農業経営とその持続性を考える際に外せない視点ではないだろうか。この視点が広く農業者に広まれば、日本でもリジェネラティブ農業に関心を持つ農業者が増え始めるだろう。
小林氏は今後の展望として、国内外の実践者や研究者が情報交換できるプラットフォームの構築を構想している。多くのノウハウが蓄積されている海外と、日本で活動している実践者をつなぎ、研究者が学術的な裏付けを与えていくことで、より大きな社会的インパクトが期待できるはずだ。
(文・鈴木 雅矩)
※当記事は「研究応援 vol.37」(リバネス出版、2025年3月発行)より引用しています。
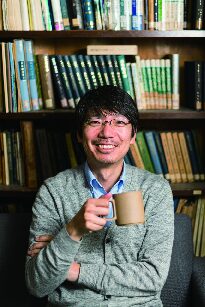
専門 農業経済学
〈研究テーマ〉ソーシャルラーニングとしてのRegenerative agricultureの普及プロセスに関する研究
1975年北海道生まれ。北海道大学大学院農学研究科を修了の後、イギリス留学。助教を経て、2016年から現職。主な研究内容は、農村振興に関する社会経済的研究として、新たな農村振興のためのネットワーク組織や協同組合などの非営利組織、新規参入者や農業後継者が地域社会に与える影響など。