
「リジェネラティブ・シティ」を生み出すインスピレーションの連鎖に向けて──『WIRED』岡田弘太郎氏と探る、都市再生の「3原則」【Inspiration Talk第1回 前編】
「サステナビリティ(持続可能性)」という言葉が社会の共通言語となる中、その一歩先を目指す概念として「リジェネレーション」「リジェネラティブ」が広まり始めている。これは、環境負荷などのマイナスをゼロにする活動に留まらず、人間社会や生態系全体をより豊かな状態、すなわち「ゼロからプラス」へと導く思想だ。
このリジェネラティブという価値観をいかに東京という大都市に実装していくか——。共にその可能性を探る連続イベント『Regenerative City Inspiration Talk〜東京からリジェネラティブな都市の未来について考えよう!〜』の記念すべき第1回が、5月21日、東京・八重洲のTOKYO LIVING LABで開催された。
シリーズの幕開けを飾るテーマは「未来の都市は、何をリジェネレーションするのか?『WIRED』日本版エディターと考える」。ゲストには、『WIRED』日本版にて「リジェネラティブ・カンパニー」号および「リジェネラティブ・シティ」号の責任編集を務めたエディターの岡田弘太郎氏を迎えた。
多様な参加者が集まった会場で、「リジェネラティブな都市」をテーマに熱い議論が交わされた。
そもそも、本イベントは、主催するFuture Food Institute(FFI)が東京建物、TOKYO FOOD INSTITUTEとのパートナーシップのもと展開するRegenerative City Tokyo構想の取り組みのひとつとして定期的に実施される。
東京建物の沢俊和氏は、「リジェネレーションとは、サステナビリティが目指す『マイナスからゼロへ』の思想を超え、気候変動などの課題に対し『ゼロからプラスへ』の回復・再生を目指す価値観」であると説明する。それは単なる原点回帰ではなく、最新テクノロジーも活用した前向きで動的な進化であり、環境や経済だけでなく、社会・文化・暮らしといった多元的な価値の全体最適を目指すものだ。
沢氏は、この実現サイクルにおける最初のステップとして、本イベントシリーズを「思想に共感する人が集まり、議論する場」として位置づける。
ファシリテーターとして参加したFFIの深田昌則氏は、リジェネレーションの思想的背景として、「FFIでは、地球環境、人間、社会、文化、経済、政治(ルールメイキング)といった諸領域を個別に解くのではなく、『統合的に考えていく』アプローチを重視している」ことも加えた。
リジェネレーションとは「地球環境の再生」と「経済社会を含めた人間のウェルビーイング」を両立させ、生態系全体が繁栄していく「NETポジティブ」な状態を目指す思想である——。両氏の説明により、本イベントシリーズが「思想に共感する人々の議論の場」として位置づけられていることが明確になった。
「未来を実装するメディア」を掲げ、カルチャーからビジネス、科学、デザインに至るまで、生活のあらゆる側面をテクノロジーがいかに変えていくのかに焦点を当てたメディア『WIRED』日本版では、「都市の未来」を考える上で、「リジェネラティブ・シティ」をテーマとした特集号を2024年9月に発売した。
「リジェネラティブ・シティと呼べる都市は、世界のどこにもまだ存在しない。今まさに進行中のものです。だからこそ、新しい都市像を提案していくことが重要だと思います」
この言葉は、会場にいる誰もが「未来の都市づくり」の最前線に立っているのだという実感を与えただろう。
岡田氏は、リジェネラティブな社会や都市を考える上での基盤として、特集「リジェネラティブ・カンパニー」制作時にアドバイザーとともに制作した3つの原則を提示する。
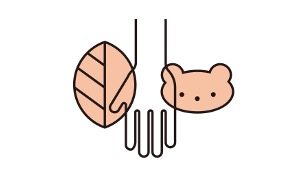
MULTI-STAKEHOLDER
“代弁者なき”ステークホルダーにポジティブな影響を与える
将来世代やマルチスピーシーズ(多種)、川や森林などの自然資本には、その声の代弁者がいない。“見過ごされてきた”ステークホルダーの存在を認識し、それらにポジティブな影響を与えるインセンティブの設計が、これからの事業活動には必要だ。その際、ガバナンスやオーナーシップの新しい仕組みを通じて、「カンパニー」を取り巻くエコシステムやコミュニティに利潤や価値を還元することが重要になっていく。
「都市開発で一度ビルが建てば数十年残ります。そのビルはいずれ、まだ生まれていない将来世代も使うことになりますが、それが建てられる段階では将来世代の声は反映されません。リジェネラティブな都市を考える上では、ステークホルダーを拡張して考える必要があると捉えています」
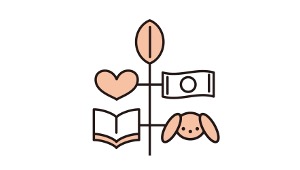
PLURAL CAPITAL
多元的な資本を生み出し、その価値を測定する
あらゆる資本はそれぞれ独立して存在するのではなく、複雑に絡み合っていることにいまや誰もが気づいている。経済資本の最大化だけでなく、その事業活動が生み出す人的/知的/物的/自然/社会関係資本とのつながりを再定義し、あらゆる資本を豊かにすること。そして、これまで見過ごされてきた多様な資本の在り方を積極的に再評価することで、その価値を社会に示していくことが、これからのカンパニーの役割となっていく。

SYSTEM CHANGE
複雑なシステムに介入し、修復する
いま社会が直面する課題がシステムに起因するものだとしたら、サステナブルやレジリエンスを追求したり、資本主義のルールのなかで得た経済資本によるフィランソロピー(慈善)で不足を補おうとしても、それはシステムの延命に手を貸すことにしかならない。いま必要なのはシステムそのものに介入し、つくり替えていくことだ。生態系や地域社会を支えるシステムは複雑だからこそ、介入するべきポイントや根本課題を特定することが重要だ。
こうした3原則を満たす「リジェネラティブ・カンパニー」の実践例として取り上げられたのが、チーズケーキ『CHEESE WONDER』を手がける「ユートピアアグリカルチャー」だ。
同社は、牛のゲップに含まれるメタンガスが環境負荷になるという課題に対して、放牧酪農を採用し、牛が草を踏み糞尿が土に混ざることで土壌が吸収できるCO2の量を増やす研究を北海道大学と進めている。これにより、牛が排出するメタンより多くのCO2を土壌が吸収する状態を目指している。
「生活者は美味しいチーズケーキを食べるだけで、環境再生に貢献できる仕組みになっています。システムそのものを再構築しながら、生活者の意識変容にも貢献する理想的なビジネスモデルだと思います」
ではなぜ、この3原則がいま求められるのか。岡田氏は、現代の東京が直面する課題にも言及する。
「2002年の都市再生特別措置法以降、大規模な再開発が進んでいますが、それを単に反対・否定するアプローチはあまり有効ではないと考えております。経済合理性で進む開発に対し、開発時に自然環境の豊かさなど、経済以外の価値を追求する、あるいはリジェネラティブな方向での開発を目指すといった、より建設的なアプローチを模索することが重要だと考えています」
その建設的な議論のヒントとして、岡田氏は世界の先進事例を挙げる。

ニューヨークの「Billion Oyster Project(10億個の牡蠣プロジェクト)」は、2035年までに10億個の牡蠣を川に投入する取り組みだ。牡蠣が持つ海水浄化能力という「生態系サービス」を活用するだけでなく、市民がその活動に参加することで、自分たちの都市環境を再生しながら新たなコミュニティのつながりを生み出している。

建築分野では、オランダのラウ・アーキテクツなどが推進する「マテリアルパスポート」にも注目する。これは建材に個別のIDを付与し、追跡可能な状態にすることで、解体後の建材を廃棄物ではなく別の場所で再利用できるようにする考え方だ。大阪・関西万博のオランダパビリオンでも採用されており、建築を自然の循環から切り離された人工物ではなく、生命循環の一部として捉え直す思想が反映されている。これは最も取得難易度が高いとされる環境認証「リビングビルディングチャレンジ」の思想にも通底するという。
「『リビングビルディングチャレンジ』の考え方は興味深く、『建築は生命循環の一部なんだ』という捉え方から始まった認証です。いままで建築は人工物として、自然環境と切り離されたものと捉えられていました。自然循環の一部として建築を捉える動きから始まっているんです」

また別の例として、イギリスで始まった法制度「生物多様性ネットゲイン」も挙げられた。これは宅地開発などにおいて、開発前と比較して生物多様性を「最低10%増加させる」ことを義務づけるルールであり、開発行為そのものに再生を組み込む枠組みだ。
そのほかにも、地域の土着の知恵や資源を活用するムーブメントである「ローテクデザイン」、ヘルシンキが発表した人間以外の多様な種(マルチスピーシーズ)のための都市に関する調査レポート「マルチスピーシーズ都市」といった事例も紹介している。
フードスケーピング事業者 「グリーンネイバーズ」が恵比寿ガーデンプレイスなどで実践する「食べられるランドスケープ」は、景観の美しさだけでなく、人々が作物を管理し、食べるというアクティビティを通じてコミュニティを育むアプローチだ。
また、東京で注目すべき動きとして、岡田氏は以下の事例を提示している。
●「みんでべ(Mind-Dev)」:
「東京R不動産」などが始めた地域の大家や地主が建築家や老舗企業と連携し、主体的にエリア開発を行う動き
●「生きもの東急不動産」:
都心のビルに鳥の巣を作り、野鳥のための生態系ネットワークを都市全体に構築しようとする取り組み
●「ニシイケバレイ」:
17代続く大家が所有物件を改修し、シェアキッチンやコワーキング、住宅などの複合施設を創り出す西池袋のプロジェクト
岡田氏は、こうした個別の取り組みを体系化・メソッド化していくことが、東京の周辺部の新しい景色を描く上で重要になる、と話す。
『WIRED』日本版が提示する「マルチステークホルダー」「プルーラルキャピタル」「システムチェンジ」という3つの原則は、リジェネラティブな都市づくりの羅針盤となる。そして世界各地の先進事例は、この原則が決して理想論ではなく、実践可能なアプローチであることを示している。
では、これらの知見を東京という複雑な都市にどう実装すればよいのか。後編では、参加者との質疑応答とグループワークを通じて浮かび上がった、東京をリジェネラティブにするための具体的な道筋と、文化的障壁を乗り越えるヒントについて探っていく。
(文・須賀原みち)
